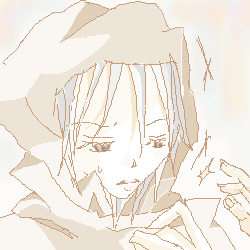
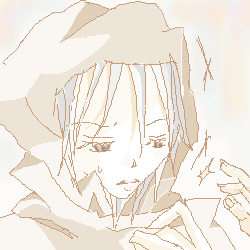

それは月夜の事。
二人は決して思いもしなかった。
一緒にいながらも常に等しい距離を保っていた千石と亜久津。
暗い夜の闇に浮かぶ月を格子越しに千石は見つめる。
足は湯殿の方へと。
ひたひたひた
誰もが寝静まる深夜に、いつも決まって湯殿を使う輩がいる。
それに千石は気がついていた。
気がついていてあえて言わなかった。触れなかった。
どうして亜久津が人の目を忍ぶように水を浴びるのか、その意味を理解しかねた。
けれど、亜久津が変わらず自分の傍にいることは事実だったし。
どうせどこにも行けないと分かっていたから放っておいた。
第一
自分の亜久津に対しての想いなど、当の本人でさえこの時はまだ気付いてさえもいなかった。
きし。
檜で作ったすのこを踏むと、少しばかり音がなる。
「誰だ。」
敏感にその小さな音を聞き逃さなかった亜久津に、千石は少し目を見張りながら口元を緩めた。
一息ついて、まるで苦笑したような微笑。
「誰って、あなたの千石清純ですよーvv」
「誰が誰のだっつの。」
「あっれー?良いのかなぁ。亜久津が着るものないと困ると思って持ってきてあげたのに。」
「っ。」
湯殿の中で息を呑む声が聞こえた。
どうやら本当に気付いていなかったらしい。
瞳をすぅと細めて口を尖らした千石だったが、すぐに口元だけを笑みの形に象る。
「良いよ。ここに置いておくからね。」
「あ、あぁ・・・」
腰をかがめて湯殿の前に置いた。
そうして立ち去ろうとした時、ふと湯殿の方へ目を向けてしまった。
目が、離せなかった。
足が固まって、動けない。
瞳が奪われる。
少し開いた扉。
いつもなら人がいたら決して戸を開けようとしないのに、その夜は少しだけ開いていた。
それは満月の力のせいか。
はたまた自分の目がおかしくなったのか。
けれど、千石は確かに"視た"
その隙間から見えた色は
月と同じ銀髪だったと。
「っ!!!」
気がついたら思わず扉を開けていて。
驚いたのは亜久津だ。
千石はそんな事はしないと読んでいただけに驚いた。
否、裏切られた気分だった。
千石の瞳は亜久津に釘付けになっていて。
橙色の大きな瞳は更に見開かれる。
「見るな!!!!」
そう叫んだ言葉とともに、千石の目前には扉が現れた。
荒荒しい扉の閉め方に、思わず我に返る。
けれど、まだ動悸は収まらない。
どくどくどく。
自分の血の脈打つ音を耳にしつつ、千石は目を閉じた。
自らを暗闇に誘う事で心を落ち着ける。
扉に左の手の平をぴったりとつけて。
額を近づけると太陽の色を持つ前髪が木に触れる。
目を閉じても今でも鮮明に眼に浮かぶ。
雪の様に白い肌。
灰色の瞳。
そうして
輝くような銀の髪。
動悸が収まらないのは千石だけではない。
亜久津もふー、ふー、と息を荒くして扉を押さえていた。
収まらない息が湯気となって立ちこむ。
見られた
見られてしまった
そんな想いが胸中に響く。
化け物
忌み子
止めてくれ。
「亜久津?」
不安げな千石の声で我に返って、亜久津ははっとした。
はっとしたが、声は出さない。
「亜久津?」
もう一度、自分を呼ぶ声。
それを聞いて、目を細めた。
胸が苦しい。
今までだって幾度となくあったのに。
どうしてだろう?
この男にだけは知られたくなかった。
「落ちついたら出てきて。俺部屋にいるから。」
「・・・・・・・・・・・・・。」
「ずっと待ってるから。絶対来て。」
淡々とした言い方は、表情が読めない。
それが恐怖となって亜久津に襲い掛かる。
ひたひたひた
足音が遠くなっていく音を耳にしながらも瞳を伏せたまま動けない。
どうなってしまうのか。
見世物にされるか。
売られるか。
慰み者にされるか・・・・
今度は自分はどんな末路を歩むのだろうかと思って心が震えた。
************
******
「・・・・・・・・・遅かったね。」
意外にも、自分を迎い入れた千石はとても穏やかだった。
もう子の刻も過ぎているので明かりなどあるはずもなく。
けれど今日は満月だから窓に腰掛けている千石の表情は伺えた。
「なんでそんな所につったってるの?」
今は暗闇に包まれているから良い。
だけど光のある所に行きたくないと思った。
「大丈夫、恐がらないで。」
「別に恐くねぇよ。」
「そっか。」
そういって笑った千石は、いつもの策略的で、嫌味たっぷりで、いかにも自分をからかって楽しんでるようなものは全然含まれていない晴れ晴れとした笑顔を向けた。
だからこそ、ためらう。
「どうする気だよ。」
「どうするって、何を?誰を?」
穏やかに千石は微笑んでいる。
まるで怯えている動物をあやすように。
「俺をだ!」
「なんで?」
くすりと目を細めて笑った。
まるでそんな必要はないというように。
「おいで。見せて。」
「俺を売るのか。」
「どうして。」
「俺を慰め物にするのか。」
「今までそんな扱いを受けていたの?」
「される前に逃げた。」
「そうしてやっと安堵の地を見つけたのに、一族は殺されて、血の繋がってない亜久津だけが生き残って、それでも追われて。」
千石は微笑みは絶やさない。
ぎっと睨んだら千石はにっこり笑う。
「大丈夫。俺は亜久津を売る気も慰み物にする気もない。」
「なんでだ。」
目を少し伏せると、銀の睫毛が瞳を隠した。
半分隠された瞳はどこかとおくを見ていて。
俯いた顔は、表情が消えていた。
「信じられねぇ。嘘だ。」
「嘘じゃないよ。」
「優しくしといて、明日になれば殺す気だろ。」
「なんで殺すのさ。」
はぁと溜息をつく。それでも亜久津から目を離さない。
亜久津は顔を上げない。
目を合わす事を避けている様に思えた。
「お前は見ただろ。」
「あぁ、亜久津の髪?」
「っ。」
「そんなん気にしてるの?」
馬鹿らし。
そんな事を呟いて、瞳を細くすると月を見上げた。
横顔が妖しく光る。
なまめかしい。
ソウ、思った。
いつもは主だなんだ、戦がなんだ、といってその顔は大人びている。
けれど、こうして月明かりの下で見ればまだ年端もいかない少年。
細い、身体。
白い小袖を一枚羽織ってるだけだからかもしれないが、その姿が妙にくっきり目にうつる。
いつもへらへらとして。
だけど、それは場を緊張させない為だと気がついた。
いつも真面目じゃないくせに、たまぁに真剣に考えているのを目にしたことがある。
「亜久津。」
月から目を離さずに千石は口を開く。
そうして、ゆっくりと顔を前に向けた。
瞳が交わる。亜久津は目を離せない。
交わる瞳は捕らえられて。
その瞳はまっすぐだった。
「お前が化け物って言われるなら、俺はなんなの?」
微笑んだその顔は、壊れていた。
あまりにも穏やかに微笑むものだから、一瞬ヒトではないかと思えた。
「おいで。」
それは、まるで命令。
でも
逆らえない自分が確かにいた。
ゆっくりと亜久津の足が前へと進んだ。
千石はそれをじぃと見つめる。
月の下でその緋色に似た瞳は輝いた。
月の明かりが照らされる。
白い足。
白い小袖を纏って。けれどすっぽりと頭から布を被っていた。
その灰色の瞳はどこか怯えた様に震える。
千石は亜久津から目を離さずに、手を伸ばした。
「・・・・・・・・触るなっ・・。」
「どうして?」
「忌むべき刻印を持って産まれてきた奴に触れると呪われる。」
「どうしてさ、綺麗なのに。」
月明かりの下で見ると、本当に銀髪だった。
水に濡れたから分かったことだが、亜久津の髪の毛はストレート。
いつものとげとげしい頭は本物ではないと知る。
膝立ちになった亜久津の前に立って、その髪の毛を手に取る。
「綺麗・・・。」
うっとりと、千石は呟いて亜久津の前にしゃがむ。
びくり。
その身体が震えるのをみて、また微笑んだ。
「大丈夫、俺はお前を捨てたりしないよ。」
「そんな話、どうして信じられる?」
にっこりと、微笑んで千石は言った。
「似たもの同士だから。」
「あぁ?」
「俺の髪ね、染料だと思う?」
「?」
「地毛だもん。」
臆す事なくそう言い放った千石に、亜久津は言葉を失う。
「この瞳も、ね。」
人差し指で示すその瞳は、赤茶。
よくみると、太陽の色に似ていた。
「赤は吉凶。赤不浄と呼ばれるモノ。」
亜久津はまだ何を言われているか分からない。
今は、微笑みは消えた。
太陽にも似たその瞳だけがまっすぐ亜久津を捕らえる。
「俺の初恋の相手はね、俺の母親だった。」
その告白に、思わず目を見張った。
灰色の瞳が大きく大きく見開かれる。
「くす、驚いた?」
「そんな話を聞いて驚かないやつはいねぇよ・・・。」
「うん、これ話したの亜久津だけだよ。」
にっこりと笑う千石に、迷いは見られない。
躊躇も見られない。
「あのねぇ、俺の母親すっごく若くて嫁いできてね。俺を産んだ時まだ15だった。だから、俺が11の時26だったんだ。」
千石は瞳を遠くに向ける。
まるで、かの記憶を追ってるように。
「凄く儚げで綺麗な人だった。童顔だったし、俺はそれを恋だと錯覚した。」
「・・・・・・・・・。」
「そう、あの日も満月だったなぁ。もしかしたら陰の大王の魔力にやられたかな。」
「何が・・・。」
「ん?知りたい?」
視線を亜久津に向けて、千石は口を緩めた。
月明かりの下、千石の表情は輝く。
その唇が、動く。
「抱いたんだ。」
「っ。」
「あはは、驚いた?」
「抱いたって、お前・・・。」
「本当、おかしいよね。俺。」
くすくすと笑う千石の瞳はどこか暗い。
けれど、その時の千石の心に嘘はなかったと亜久津は感じた。
「母上は実の息子に裏切られ、女にされた。綺麗だったよ。白くて、細くて。抵抗したけど成長した俺に敵うはずもなく。夫の名誉の為に声も出せず。・・・・・・むごい事をした。」
「その母親は今・・・?」
「死んだよ。」
「!」
「次の日、朝露の下に、母上は横たわっていた。事故だとされたけど、あれは事故じゃない。」
俺が殺したんだ。あれは自殺だった。
微笑を絶やさずに千石は言った。
ためらわずに言う千石から亜久津は目を離せない。
火の髪が揺れる。
微笑んだから、揺れてみせた。
「"ここ"から母は飛び降りた。」
立ちあがると、先程まで自分が座っていた窓のへりに腰をかける。
いとおしそうに木を撫でる千石の瞳は細まる。
「俺は、ずっと、ずぅっとそれからここで月を眺めている。朝は母上が見ていた風景をここから眺める。」
「…………。」
「好きだった。例え間違った恋だったしても、あれは恋だった。」
「…………ああ。」
やっと亜久津が搾り出した言葉はソレだ。
その言葉があまりにも亜久津らしくて千石は視線を上に上げると笑った。
「母上がが死んだその日、俺の髪と瞳は真っ赤に染まった。」
「そんな事があるのか?」
「さぁ?もしかしたら母の最後の抵抗だったのかも。」
口を緩く弓張り型に吊り上げる。
不敵な微笑が浮かびあがった。
「その色は怒りであり、憎しみであり、罪の烙印だったのかもしれない。」
「…………。」
「それから父上が死んで、俺は当主になった。」
それを聞けば、いかに千石が辛い状況にいたか想像できる。
けれど千石はそんな亜久津の表情を読み取ったのか軽く頭を振った。
「違う。だって周りは誰も気付かなかったんだもの。誰も俺がそんな悪い人間だって信じなかった。」
そういう千石の横顔はどこか切なげで。
罪に問われたわけでもないのにその顔は苦しげに微笑んでいる。
「だから、この髪と瞳を見て、みんな驚いて俺を恐れたよ。」
「……………不幸を呼ぶ者だと?」
細い言葉に千石は顔を上げた。
紅い瞳が亜久津を見る。
揺るぎないその瞳を亜久津は真正面で捕らえた。
「そう。でも誰も責めなかった。」
「でも、責めて欲しかった?」
尋ねたら、今度は泣きそうに笑った。
その顔は
今でも亜久津の心に深く刻み込まれている。
―――――――
続きませう。
後どんぐらい?一つ?二つ?
千石っちゃんの秘密が明らかにされましたねん☆
私もよくもまぁこんな面倒くさい設定を考えたもんだと思います。
頑張れ私、あと一息だぁよ!!!(応援?)
return